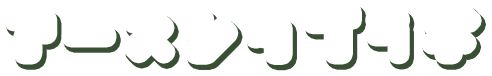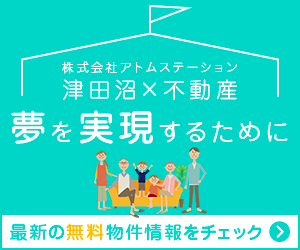自給自足の一環として、自宅で米麹を作る方法をご紹介します。
米麹は、味噌や醤油、甘酒など、日本の伝統的な発酵食品を作るのに欠かせない素材です。
特に、お味噌汁を毎日飲む人や、醤油を使った料理を好む人には必需品のアイテムと言えるでしょう。
では、早速見ていきましょう。
広告
手作り米麹の作り方
米麹を作るのに最適な時期は、高気温多湿の梅雨の時期6月~8月と言われています。
この時期は、麹菌が元気に活発になる時期で体験教室もこの期間に催されることが多いです。
とは言え、麹菌を作るのに重要なのは最適な温度36℃~38℃を常に一定に保つということです。
そのため、冬だろうが夏だろうがこの温度になるように管理しなければなりません。
必要な道具
手作りで米麹を作るためには、以下のような道具が必要です。
今回は、初心者用にkg単位ではなく、トライしやすい量で紹介します。
- 米3合(450g)
- 麹菌1.5g(インターネットや専門店で入手可能)
- 蒸し器
- 蒸し布(米に直に触れる)
- ザルとボール
- 大きめのトレイまたはバット(蒸した米を乗せる用)
- 清潔な布巾(米に直に触れる)
- しゃもじ
- 温度計
- ふるい(または茶こし)
- 発酵用の箱または容器(専用容器付きのヨーグルトメーカーなどだと尚良し)
- 寒い時期には毛布などの包む布(発酵用機械を使わず箱などで代用する場合に必要)
前述したように、温度管理が重要なのでそれをちゃんと遂行できるための道具がほとんどになります。
また、米麹つくりで使用する布製品は事前にキレイに洗濯をしておきましょう。
米麹の作り方手順
米麹つくりの工程は、大きく分けて4工程です。
「米を洗って浸水」「水切りして蒸す」「蒸し上げてから保温」「保温中の手入れ」をおこないます。
さらに詳細な手順は以下の通りです。
- 洗米する
ボールの上にザルを乗せ、その上に3合分のお米をに入れます。
溜まった水を混ぜるようにして洗い、ざるを引き上げてボールの水を捨てます。
濁りが消えるまで3~4回繰り返しますが、コツとしては米の粒を壊さない洗い方を意識しましょう。 - 浸水する
洗った米を夏場は3~5時間、冬場は12時間~1日水に浸けます。
水浸のコツは一粒取り出し、指腹で米粒を押して砕ければ良し、硬ければ再び水に浸けます。
水につけている間、雑菌や埃が入らないようにラップなどで密封しましょう。
この時、ボールの上にザルがかぶさった状態で水を張っていると次の水きりでラクです。 - 水切りをする
この工程はとても重要です。
蒸した際に、米がベチャベチャにならないように、米粒を壊さないように2~4時間ザルに入れて放置します。
この時も、上はラップをするなどして埃や菌がつかないようにしましょう。 - 蒸し器で蒸す
40分~50分ほど蒸すため、空焚きにさせないためにも蒸し器にはたっぷり水を入れておきましょう。
水切りした米を蒸し布で包み蒸し上げます。
大きめの蒸し器が無い場合は、やかんなどでお湯を沸かし、蒸し器の水が無くなる前に足しましょう。
米の仕上がり目安は、一粒を指腹でこすった時に芯が無く、餅のように伸びる感じがすれば出来上がりです。 - トレイに移して粗熱を取る
蒸した米は高温のため、しゃもじで清潔な布を敷いた大きめのトレイまたはバットに乗せます。
この時も、米粒を壊さないように乗せていきます。
温度計を使い、蒸し米の温度が40℃~45℃になるまで粗熱を取ります。 - 種麹を均一に振りかける(スピード重要)
粗熱が取れ適温になった蒸し米に、ふるいや茶こしで素早く均一に種麹を振りかけます。
ここではポイントが2点あります。
・種麹がかかっていない部分は発酵しないため、かけ忘れがないように均一に振ること
・この時点で35℃を下回らないように手早く終わらせること - 素早く布に包み保温す(スピード重要)
種麹を均一に振りかけた蒸し米を、清潔な布にくるみ、発酵用の箱または専用容器付きのヨーグルトメーカーに入れます。
この時、温度計も一緒に入れて保温環境が35℃~40℃に保たれるように管理出来るようにしましょう。
30℃を下回ると、麹金の発酵が鈍るため失敗のリスクが上がります。
その逆で、40℃を超える場合は適温になるように温度を調整しましょう。 - 12時間おきに手入れ(スピード重要)
保温開始から12時間後に1回目の手入れをおこないます。
清潔なトレイまたはバットに布を敷き、米をほぐすように広げます。
酸素を全体にいきわたらせるイメージでほぐしましょう。
更に12時間後に2回目の手入れをおこないます。
1回目同様に、麹の手入れをおこないます。
この段階からは、発酵が進んできているため水滴や水蒸気も気にしましょう。
保温機などに水滴がついている場合はキレイにふき取り、米にきれいな布をかぶせて余分な水蒸気を吸収するようにしましょう。
様子を見て、温度とは別に蓋を開けるなどの水分の管理も必要になってきます。 - 6時間おきに手入れ(スピード重要)
更に6時間後、3回目の手入れをおこないます。
1回目同様、酸素を全体にいきわたらせるイメージでほぐします。
更に6時間後に4回目の手入れをおこないます。
同じように手入れをします。
容器に入れたら、今度は米麹の乾燥を防ぐために被せていた布巾を濡らして軽くしぼり、改めて米麹に被せます。 - 最後の追い込み(12時間)
4回目の手入れから6時間後に温度帯が40℃になるように調整しましょう。
そのまま40℃をキープさせた状態で6時間待つと、甘くて美味しい米麹が完成します。
米同士がくっつき、1つの塊となり、栗のような甘いによいと菌糸がフワフワと漂っていれば成功です。
トレイまたはバットに移して、ほぐして冷ましてから小分けにしていきます。
最初の保温から48時間で米麹ができました。
慣れるまでは、麹の手入れや温度調整に苦戦するかもしれませんが、慣れると短時間で作れるので手軽にできる自給自足アイテムとしておすすめです。
まとめ
手作り米麹は、少しの手間と時間をかけることで、家庭でも簡単に作ることができます。
自分で作った麹を使って、健康で美味しい発酵食品を楽しむことは、自給自足生活の大きな喜びの一つです。
皆さんもこの機会に、手作り米麹にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
自然と共生する生活を送る私たちにとって、米麹はただの食材ではなく、生活の一部です。
この記事が、皆さんの自給自足ライフに役立つことを願っています。
次回も、エコで健康的な生活のヒントをお届けしますので、お楽しみに!
広告