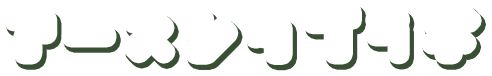家庭菜園をしていると「コンパニオンプランツ」という、聞きなれない言葉を見聞きします。
この言葉を見聞きするタイミングはおそらく、育てている作物が途中で枯れてしまったり、病害虫被害が多くなった時ではないでしょうか?
生育の妨げを緩和するために必要な「何か」であることは確かなコンパニオンプランツ。
今回は、そんなコンパニオンプランツについてを分かり易く解説します。
広告
コンパニオンプランツとは?
コンパニオンプランツとは、相性の良い植物同士を一緒に植えることで、害虫の防除や肥料の節約、収穫量の向上などの効果を期待できます。
そのためコンパニオン(仲間)プランツ(植物)と言われ、相性の良い植物の組み合わせを意味して使います。
日本語で表現すると共存植物や共生植物、共栄植物と書きます。
自然界の相互作用を利用した、持続可能な農業の一形態と言えるでしょう。
コンパニオンプランツのメリット
コンパニオンプランツを利用することで、化学肥料や農薬に頼らずに健康的な野菜を育てることが可能です。
また、植物同士の相乗効果で土壌の改善や病気の予防にもつながります。
また、同時に数種類の作物を栽培できるのでスペースを有効活用することができます。
そのため、連作障害を引き起こす野菜を栽培する際にはコンパニオンプランツを用いることで、植える場所を変える手間やコストを削減できます。
家庭菜園でのコンパニオンプランツの活用法

コンパニオンプランツの活用方法には「混植」と「間作」と「輪作」の3通りの植え方があります。
どういう違いがあり、どんな場面で活用するかをここでは説明します。
混植とは
混植とは、同一の場所に複数の異なる作物を植えることを言います。
例えば、畝を作ってメインの作物を栽培している場合は、同じ畝にサブとなる作物(今回で言うとコンパニオンプランツ)を植える行為です。
混植の仕方にもいろいろあります。
同じ穴に植える混植方法
文字の通り、同じ植え穴に一緒くたに植える方法です。
この混植方法は、コンパニオンプランツの根を介して微生物で土壌を安定または活性化させる手法で、例えばニラの根に共生する拮抗菌が分泌する抗生物質を利用してトマトやナスの連作障害を抑える効果があります。
同じ穴に混植する場合は、根が深く伸びるタイプなのか、浅く伸びるタイプかで組み合わせを考えると混植の相性が良くなります。
囲んで植える混植方法
メインになる作物の周りにコンパニオンプランツを植える混植方法です。
主にバンカー作物で囲むことが多い混植方法で、害虫が寄り付きやすい作物に使う手法です。
バンカー作物は、益虫(害虫を捕食する虫)に好まれる性質があるため害虫が寄り付く作物の近くに植えることで、害虫を退治してくれます。
これをバンカープランツと言います。
その他に、虫が嫌う臭いを発する植物や作物もあるので、メインの作物の害虫事情を考慮して周りに植えるコンパニオンプランツを決めましょう。
交互に植える混植方法
メインの作物を1株ずつ、または5株ずつにつきコンパニオンプランツを間に植える混植方法です。
規則的に間にコンパニオンプランツを植えるやり方なので、1~10株のどの間隔で間に植えるかは畑の都合を考えながら決めると良いでしょう。
組み合わせの例としては、キャベツ10株ずつの間にソラマメを植えるというイメージです。
間作とは
間作(かんさく)とは、畝のある畑で2種類以上の作物を一部重ね合わせた期間で栽培する方法です。
メインの作物を畝で栽培し終えた空いた期間に、畝間で他の野菜を栽培します。
そうすることで、時間とスペースを有効活用できます。
輪作とは
輪作(りんさく)とは、コンパニオンプランツを同時に植えることではなく、リレー方式に栽培する方法です。
そのため、リレー栽培とも呼ばれます。
同じ作物を何年も同じ場所で栽培すると、土壌の栄養が偏り病害虫に侵されやすくなります。
しかし、栽培後にコンパニオンプランツを植え付けることで、土壌の栄養が整えられまた同じ場所で栽培できるようになります。
まとめ
コンパニオンプランツは、共生植物と言われ相性の良い植物を指します。
家庭菜園においてコンパニオンプランツを活用することは非常に有効な方法です。
化学物質に頼らず、自然の力を借りて健康的な野菜を育てましょう。
私たちの健康と地球の未来のために、コンパニオンプランツの知識を活用して、豊かな家庭菜園を実現してください。
以上、自給自足ライフを楽しむ一助として、コンパニオンプランツの基本をお伝えしました。
皆さんの家庭菜園が、より豊かで楽しいものになりますように。
どうぞ、この情報を活用してくださいね。
広告