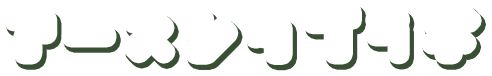近年注目され始めている「リジェネラティブ農業」を皆さんはご存じですか?
人が自分の健康を気にかけ、病気になれば病院にかかります。
ごく当たり前のことですが、地球が健康を損ねた場合は誰がそれを直してくれるのでしょうか。
今回はそんなお話がメインになる、リジェネラティブ農業についてご紹介します。
広告
リジェネラティブ農業とは
リジェネラティブは英語で「regenerative」と書きます。
意味は「再生」や「回生」ですが、「リジェネラティブ農業」と呼ぶ場合は「再生させる農業」という意味になり日本では「環境再生型農業」と呼ばれています。
これは、土壌を良い状態に保つというだけでなく自然環境を回復させるための農法を指します。
地球の温暖化による気候の悪化は、自然環境を回復することで対策できるという発表がされています。
農業とは少し逸れた話のように感じるかもしれませんが、実はそうでもありません。
土壌が健康である場合、多くのCO₂をその地に吸収することができます。
アメリカのNPOであるロデール・インスティチュートは、「現存の農地がリジェネラティブ農業になれば、世界の毎年のCO₂排出量の100%を土壌に隔離することができる」と予測しています。
リジェネラティブ農業の方法と例
リジェネラティブ農業をおこなうことで、土壌が健康になるだけではなく温暖化への抑止にも大きなアインパクトとなります。
そんなリジェネラティブ農業はどうやっておこなえばいいのでしょうか。
具体例としては「不耕起栽培」「輪作・間作」「被覆植物の活用」「有機農法をする」「家畜を飼う」です。
詳しく見ていきましょう。
不耕起栽培をする
不耕起栽培は欧米や南米を中心に広がっている農法です。
字の通り、土を耕さずに作物を栽培する方法です。
不耕起栽培をすることで、地中の微生物と植物が共生し他の生き物が生活しやすい環境を作るサイクルが生まれます。
以前に不耕起栽培について書いた記事があるので、詳しくはこちらをご確認ください。
輪作(リレー栽培)や間作をする
連作をすると土壌の栄養バランスが偏り、地中にいる微生物やミミズ類などの生態系バランスが崩れてしまいます。
そこで、輪作(リレー栽培)をおこなうことで、土壌の栄養バランスを回復させるようにします。
輪作する際は、相性の悪い作物を次に植えてしまうと土壌の回復望めないため、コンパニオンプランツを考慮する必要があります。
被覆作物(カバークロップ)の活用
メインの作物を栽培していない期間は、雑草の抑止や土壌浸食防止のためにクローバなどのマメ科植物を植えます。
地面を露出させずに覆うように植物を植えることで、土壌を肥やしてくれて且つ土壌へのCO₂の吸収がされやすくなります。
これらに適した植物を被覆作物(カバークロップ)と呼びます。
有機農法をする
化学肥料や農薬を使わずに、有機肥料を使うことで健康的な土壌にします。
また、化学肥料や農薬を使わないことは需要を減らすことになるため製造時のCO₂の削減にもつながります。

家畜を飼う
家畜を使い除草するのはもちろんですが、家畜に食べられた葉は再生しようと光合成を活発におこなうようになります。
そうすると、植物は栄養であるCO₂を取り込もうと働きかけます。
また、家畜が農地を歩き回ることで手折れた植物や踏みしだかれた地面は他の生物の住みやすい環境になります。
そうすると、様々な生物が住み着き土壌は豊かになります。
自給自足の生活にどう生かせるのか?
ここまで読んでいただいた人は、薄々と気付いていたかと思います。
そうです、田舎で自給自足をしていた場合は自然とリジェネラティブ農業ができてしまうのです!!
家畜を飼うためのコストや、日本での不耕起栽培には少し課題が残るところですが、それ以外は無理なく取り入れられる範囲です。
もしかすると、知らないうちにリジェネラティブ農業を無自覚でやっていたという人もいることでしょう。
自給自足で自然と共生することが、リジェネラティブ農業(環境再生型農業)なのです。
まとめ
リジェネラティブ農業は「再生させる農業」という意味になり、日本では「環境再生型農業」と呼ばれています。
作物のために土壌を良い状態に保つ、という事ではなく自然環境を回復させるための農法を意味しています。
具体例としては、「不耕起栽培」「輪作・間作」「被覆植物の活用」「有機農法をする」「家畜を飼う」です。
自給自足で家庭菜園をしている場合は、知らないうちにリジェネラティブ農業に取り組んでいる可能性があります。
この機会に、自然環境を念頭に置いた自給自足をしてみてはいかがですか?
広告