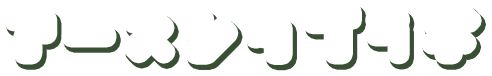自給自足ライフを送るなら、マイ味噌作りにもトライしてみましょう。
米麹を作れるようになったら、手作り味噌が作れるようになります。
手作りの味噌は、市販のものと比べて好みの味に調整することができるので格別の味わいがあり、作る過程も楽しいです。
それでは、米麹を使った手作り味噌の作り方をを、必要な道具と手順を交えてしょうかいします。
広告
手作り味噌作りで必要な道具
早速、米麴を使った味噌作りに必要な道具を紹介します。
以下の道具を揃えてくださいね。
- 大量の大豆を煮る鍋(圧力鍋だと楽ちん)
- 大豆を潰す道具
ビニール袋に入れて足でつぶす場合は、清潔な袋と輪ゴム(チャック付き袋でも可)
ミンチ機やフードプロセッサーでも問題ないです - 大きめのボール
- ザル
- 霧吹きまたはハケ
- 味噌桶または保存容器(チャック付き袋でも可)
- へら
- 重石
米麹を使った味噌の作り方



今回紹介する手作り味噌は、出来上がりが約2.5kgの塩分約10%の味噌です。
初心者向けとして、カビが生えにくい甘口味噌の作り方で紹介しますので、コツを覚えたら好みの味に調整してみてください。
- 米麹:1kg
- 大豆:500g
- 塩:295g
- 米焼酎やホワイトリカーなどのアルコール(カビ対策用)
夏場に作る場合は2ヶ月以上の熟成期間を、冬場の時期は3ヶ月以上の熟成期間を必要とします。
取り掛かる前に、どの季節で作るかも加味すると失敗のリスクを減らせます。
- 大豆を浸水
よく洗った大豆を、水を張ったボールに浸し10時間~15時間放置します。
寝る前に浸けておくとスムーズです。 - 大豆を煮詰める
ふやけた大豆を圧力鍋に入れ、大豆より4~5cm程の高さまで水を入れます。
沸騰して灰汁取りしたら蓋を閉め、水蒸気のシューという音が聞こえたら弱火にします。
弱火で30分煮込んだら、煮え具合のチェックをします。
5~6粒を指でつぶし、8割が潰れれば良い塩梅です。
逆に、割れるように潰れた場合は再度煮込みましょう。 - 冷やす
ザルを使い、大豆と煮汁を分けます。
煮汁はこの後も使うので、大豆と煮汁を30℃以下になるまで冷やします。
30℃以下にしないと、麹菌が弱り失敗する確率が上がります。 - 大豆を潰す
粒が残らないように、用意した道具を使って大豆を潰していきます。
清潔なビニール袋に入れて、足で踏んで潰すとムラなく時短で潰すことができます。 - 混合させる
ボールに煮た大豆1.1kg(元は500gの大豆)、大豆の煮汁240cc、米麹1kg、塩295gを計量して入れ、ムラなく混ぜていきます。
ここで重要なのは、必要な量をしっかり計ることです。
手順としては、麹に塩をむらなく混ぜ込み、30℃以下になった大豆を加えて大まかに20回ほど混ぜ込みます。
その後、30℃以下になった煮汁を円を描くように加えながら、下からすくって上から抑えるように混ぜ込んでいきます。
力を込めた状態で、ムラができないように60回ほど混ぜ込みます。 - 味噌団子を作る
ムラなく混ぜ合わせられたら、ボール内で押し固めます。
それを更に、大きなおにぎり程の量を手に取り、丸く固めます。
硬さの目安は、両手でパカッと割れるぐらいの硬さで良い塩梅です。 - 容器に詰めていく
丸く固めた味噌団子を、容器に詰めていきます。
用意した保存容器(チャック付きの袋やタッパー、プラスチックの樽など)に丸めた味噌団子を入れたら、1玉ごとにパンチをして空気や隙間を無くすように平らにしていきます。
更に2個目を入れてパンチ、味噌団子が無くなるまで繰り返します。
空気や隙間はカビの発生しやすい環境になるため、容器内で隙間ができないように注意しましょう。 - カビ対策
蓋をしめる前に、表面の味噌に塩を振りかけます(化粧塩をおこなう)。
チャック付きの袋などで保管する場合は、カビ対策用に準備したアルコール(米焼酎やホワイトリカーなど)を霧吹きで表面に吹きかけることでも代用できます。 - 重石を乗せる
出来る限り空気を抜くために、ビニール袋を使っている際は真空になるように意識して平らにならしましょう。
閉じ部分や底にシワが出来てないか確認し、シワはキレイに平らに伸ばしましょう。
タッパーやプラスチックの樽などの場合は、ラップをし、その上に蓋を乗せて重石を置きます。
重石を乗せる意味としては、数ヶ月の熟成期間中に水分と固形物に分離するのを防ぐためです。
そのため、重石を乗せて管理する方法がおすすめと言えるでしょう。
(密封したら、シールなどで作成日を書き貼ると管理や今後の味噌作りの役に立ちます) - 熟成させる
味噌は生き物です。
人間と同じように、快適な温度と苦手な温度があるので、家の中で過ごしやすい温度で安定しているリビングなどに置き、管理できるようしましょう。
・15℃以下、35℃以上は避ける
・直射日光を避ける
・夏場の熟成期間2~3ヶ月
・冬場の熟成期間3~6ヶ月
管理やお手入れの仕方
チャック付きの袋で管理している場合、発酵により袋がパンパンに膨れてきます。
こまめに空気を抜いてあげましょう。
また、分離で水分が出てきた場合は、袋の寝かせる向きを変えて水分のムラを分散させるようにしましょう。
熟成中に白い粉(チョーク粉)のようなものが出る場合がありますが、「チロシン」というアミノ酸の一種なので食して問題ないです。
急激な熟成温度の変化で出やすくなります。
逆に黒いポツポツが出たら、カビなのでスプーンでその部分だけそぎ取り、表面の味噌に塩を振りかけます(化粧塩をおこなう)。
または、カビ対策用に準備したアルコール(米焼酎やホワイトリカーなど)を霧吹きで表面に吹きかけます。
基本は空気に近い表面上に出ますが、放置すると内部にまで広がるので見つけ次第すぐ取り除きましょう。
その他、緑色のカビもあります。
タッパーや樽などで熟成管理している場合の天地返し(混ぜ直し)は、必須ではありません。
やると発色や香りが良くなる気がしますが、熟成が順調であればそのままでも良いです。
熟成が遅い場合には、発行を促す意味で天地返しをおこなってください。
目安としては、熟成期間2週間~4週間辺りに判断で良いです。
まとめ
手作り味噌は、時間と愛情を込めて作ることでその価値が何倍にもなります。
自分で作った味噌は、料理の味を引き立てるだけでなく、健康や環境にも優しい選択です。
自給自足の生活を目指す皆さん、ぜひチャレンジしてみてください。
自然と共生する生活を送る私たちにとって、手作り味噌は、ただの調味料ではなく、ライフスタイルの一部です。
この記事が、皆さんの手作り味噌作りの一助となれば幸いです。
では、また次回の記事でお会いしましょう。
どうぞよろしくお願いします!
広告